心に響いた内容を列挙
・「パーソナリティ5因子モデル」・・知的好奇心、良識性、外向性、協調性、情緒不安定性でパーソナリティを評価
・知的好奇心スコアが低く、良識性スコアが高いと共和党支持の傾向
・知的好奇心が高いと民主党支持の傾向
・知的好奇心でスコアが高く、協調性で低スコアはリブデムの特徴
・5因子モデルで有権者をカテゴリー化してそれぞれに応じたターゲッティングをする
・モテない白人男性=「インセル」は社会から疎外され、怒りを溜め込んでおり、いとも簡単に煽動できる
・「認知バイアス」・・最初の質問で次の質問の答えが影響されるバイアス。これを利用する
例:見知らぬ女性に「あなたは幸せですか?」と聞くと高確率で「はい」と答える。「高校の同級生であなたより成功している人はいますか?」と質問したあとで「あなたは幸せですか?」と聞くと「はい」の確率が大幅に低下。
・保守系メディア「foxニュース」は大げさなナラティブを多用して、視聴者の怒りを刺激。「感情ヒューリスティック」(論理的に考えられなくなる)、知的ショートカットを選ぶ。
・foxニュースは「あなた達は普通のアメリカ人です」とアイデンティティを吹き込む。「私達は」という言葉を多用。視聴者はアイデンティティが脅かされるかどうかを評価基準にしてしまう。
・自分と違う意見が示されると、アイデンティティへの攻撃と感じ、なおさら従来の信条に執着してしまう。(心理的リアクタンス)
・メッセージをカスタマイズして計量心理学上のプロファイルと一致させれば、人間の行動を予測するだけでなく、人間行動に変化を起こせる
・フェイスブックでAの行動を予測。「いいね!」10個でAの職場の同僚より予測できる。150個でAの家族より正確に行動を予測できる。300個でAの配偶者より正確に行動を予測できるようになる。
・ケンブリッジ・アナリティカはフェイスブックのデータを閲覧できるようにした。適当な名前、思いついた州をキーボードに叩くと、その名前の一覧が表示され、顔写真、勤務先、自宅、子供、子供の学校、自家用車、前回誰に投票したか、などがリアルタイムで見えるシステムを作った。
・ナルシシズム、マキャベリズム、サイコパシーはダークトライアドと言われる。パーソナリティー5因子に当てはまらない。ダークトライアドと神経症集団は衝動的怒り、陰謀論に傾きやすいためターゲットにされる。
・フェイスブックにおいて、エンゲージメントの向上こそが最も重視する指標。
・「ルーディックループ」「強化スケジュール」によってユーザーがフェイスブックを際限なくスワイプさせている。これはスロットマシーンを際限なく引いている心理状態と差がない。
・インターネット誕生で人と人とのバリアが取り払われて、世界中の誰もが自由に繋がれるようになると期待していた。しかし人々はソーシャルメディアに何時間も過ごし、似たような思考、趣味の人をフォローする。キュレーションされたニュースを読むようになり、認知セグリゲーションを引き起こし、ユーザーはそれぞれの情報ゲットーへ隔離され、クリック中毒のような極端な行動に走らされる。フェイスブックのいうコミュニティとは「ゲーテッドコミュニティ」である。
~~~
この本を読んで恐ろしいと感じたことは、全てノンフィクションであり、SNSの情報が全く筒抜けであること、これらの情報を他の情報と組み合わせて心理学的分類を行い、人間一人一人を分類し、個別に広告、ニュースを流すことで個人の行動変容を促し、他人に知らないうちに行動を操られる可能性があるということだ。
ケンブリッジ・アナリティカは南国やアフリカの小国で選挙に介入し、その後アメリカの大統領選挙で暗躍した。ケンブリッジ・アナリティカは解体されたが、この事例は他人事ではない。ルールや法整備が未熟なネット社会であるからこそ、ユーザーは自衛しないといけないと認識した。


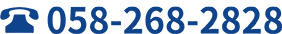
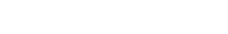
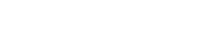
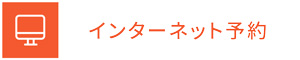

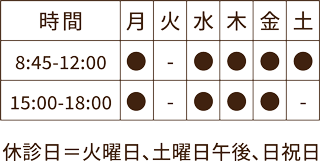


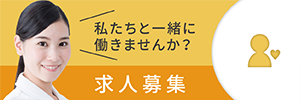
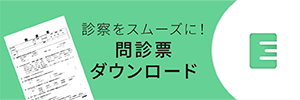



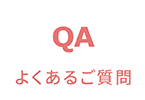


コメントする